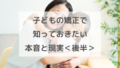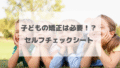子どもの矯正治療、本当に今すべき?正しく知って選ぶために大切なこと
日々、たくさんのご家族から子どもの矯正相談を受けていると、ある共通の“思い込み”に気づかされます。
それは、 「子どものうちに矯正しておけば、大人になってからの矯正は必要なくなる」 「便宜抜歯を避けるためには、早いうちから矯正を始めたほうがいい」 というものです。
実際にこうした考えをお持ちの方は多く、なかには周囲の人やかかりつけの先生から言われて、そのまま信じているというご家族もいらっしゃいます。
もちろん、子どもの時期にしかできない矯正治療は確かにあります。ただし、すべての症例において「早ければ早いほどいい」とは限らないのが実際のところです。
“光”の部分:本当に早期治療が必要な場合
たとえば「反対咬合(受け口)」のお子さんは、早期治療がとても重要です。
可能であれば5〜6歳のうちに相談していただき、遅くとも8歳までには治療を開始するのが理想です。そうしなければ、将来的に外科手術が必要になる可能性が高くなるからです。
この時期の受け口治療では「フェイスマスク(上顎前方牽引装置)」という装置を使用します。毎日10時間程度、半年ほどの装着で徐々に改善していくため、親御さんとお子さんのご協力があってこそ成り立つ治療です。
ただ、もしその時期を過ぎてしまったとしても、大人になってからの外科矯正(顎変形症)は保険が適用され、手術で骨格ごと調整することができます。費用も自己負担80〜90万円ほどで、仕上がりも良好ですので、必要以上に不安を感じる必要はありません。
“闇”になり得る部分:すべての「ガタガタ」が早期治療の対象ではない
一方で、近年特に多く感じるのが「ガタガタの歯並びを指摘されて相談に来られる」ケースです。
前歯の凸凹が気になる気持ちはとてもよく分かります。ただ、実はこの“ガタガタ”のうち、子どもの矯正だけで本質的な改善が見込めるケースは全体の2割程度なのです。
なぜなら、歯並びは「歯の大きさ」と「歯を支える骨(顎)の大きさ」のバランスで決まっており、現在の歯列を単純に拡げても骨のサイズ自体は変わりません。
よく使用される「拡大床」という装置は、歯列のアーチを広げることはできますが、それは歯が外に傾いて広がっているだけであり、根本的に骨格が大きくなったわけではないのです。
つまり、前歯のスペースを一時的に確保できても、後から生えてくる犬歯や小臼歯のスペースが足りなくなってしまうこともあります。
さらに、無理な拡大によって、控えていた犬歯の歯冠が隣の歯(側切歯)の根にぶつかり、歯根を吸収してしまうというリスクも報告されています。これは、その歯の寿命に影響を及ぼす可能性すらあるのです。
拡大床は否定しません。けれど目的を見誤らないこと
こうした理由から、「前歯がガタガタだから拡大床で広げましょう」だけでは不十分なのです。
当院でも拡大床は使いますが、それは上下の歯列幅にズレがある「交叉咬合」や、成長にエラーが起きそうなケースに対してです。また「受け口」や「出っ歯」などが絡む場合には、拡大床が有効な症例もあります。
大切なのは「なぜこの装置を使うのか」という理由が明確であることです。
前歯のガタガタがあっても、将来的に本人が気にすることがなければ、矯正をしないという選択も尊重されるべきだと思います。逆に、見た目を気にして悩んでいるお子さんには、しっかりとした診断の上で適切な治療をご提案しています。
誤解を生まないために。大人の矯正でも治る「ガタガタ」の現実
少しだけ現場の本音をお話しすると、家事や育児に加え、習い事や塾で毎日が忙しいご家庭に対して、「将来、大人の矯正でも治せるガタガタ」のために通院と費用の負担を強いることには、私自身慎重でありたいと思っています。
また、中には「子どもの矯正を始めれば、どうせ大人になったときも自分の医院で継続してくれるだろう」と考えて、積極的に早期治療をすすめる医院もあると聞きます。医院経営の観点からは理解できますが、患者さんの人生全体を考えたとき、本当に必要なことを見極めていきたいものです。
最後に
矯正治療は、人生の中でもそう何度も経験するものではありません。だからこそ、何が“正解”なのか迷うこともあると思います。
そんなときには、「どんな目的で、どんな方法で、どんな未来を目指しているのか」を一緒に考える時間を大切にしたいと、私は思っています。
すべてのお子さんにとって最適な治療は異なります。ご家族の思いに寄り添いながら、無理のない、納得のいく選択ができるようサポートしていきますので、どうぞ安心してご相談ください。